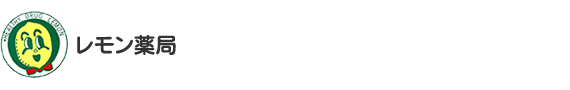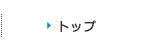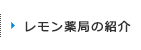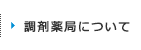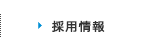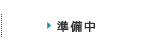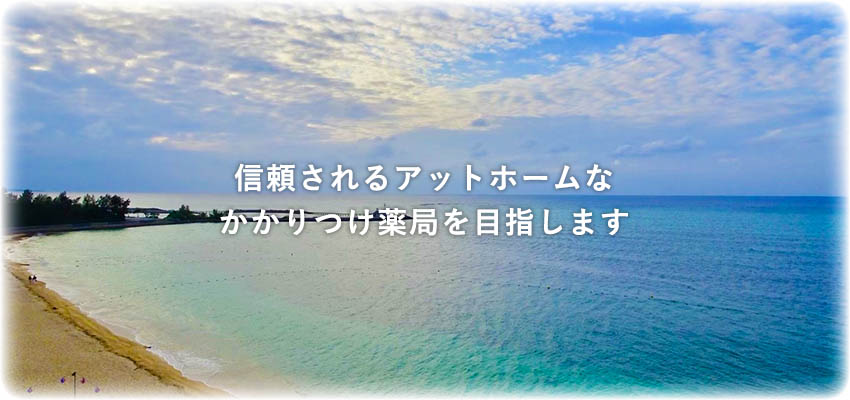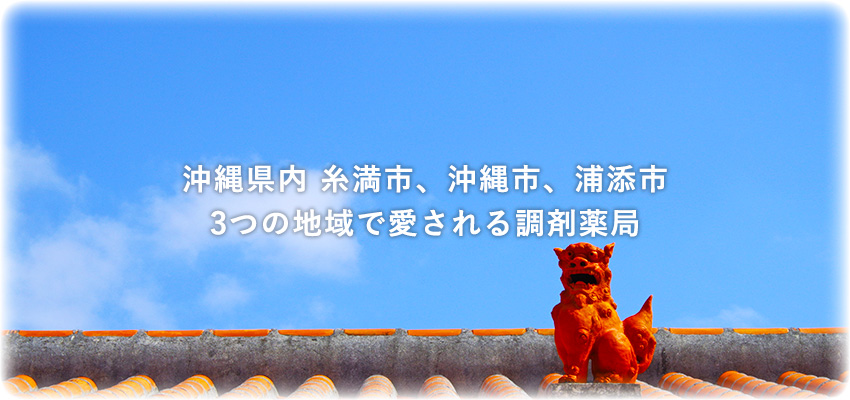新着情報
地域に信頼されるパートナーへ
私たちは、現在沖縄県内で糸満市、沖縄市、浦添市3つの地域で5施設の調剤薬局をさせていただいています。患者様をとおして病院、クリニック等からの処方せんのお薬を調剤し患者様の生活背景を想像しながらしっかりと説明し服用する時の注意点を伝える大事な役割を担っています。レモン薬局では薬局内の業務だけではなく、薬局から外に出て地域の皆さまの寄り添い、しっかりとコミュニケーションをとり、地域の皆さまに信頼されるパートナーでありたい、それが私たちの理想とする薬局の姿です。